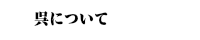- 「呉にはもう随分長い間、行かない。この前に行つたのがいつだったか、はつきりしない位で、その印象だけが頭に残つてゐる。一體に東海道沿線の町といふのは東京から下關に至るまで、どこも同じといふ感じがするのは、汽車で移動する人間の數が多すぎるからかも知れない。いつか廣島の大きな喫茶店にゐて、二日酔ひのせゐもあつたのだらうが、窓越しに見た町の風景が東京の銀座と少しも變らないので自分がどこにゐるのか解らなくなつたことがあつて、その東京の銀座も現在では、昔の銀座ではなくて東京銀座とでも呼んだ方がよささうな個性がない場所になつてゐる。しかし呉は呉といふ町の感じがする。東海道線から少しばかり逸れてゐる爲なのか、町の地形なのか、それとも人情がさうなのか、理由はどうにでも付けられるとして、かなめ旅館で朝、目を覺して寝床の中で廣島工場のキリン・ビールを飲む時から、もう自分が呉にゐることが直ぐに感じられた。キリン・ビールの廣島工場のが東京のなどとは比較にならない位、旨いことは確かである。併しそれならば、廣島にゐる氣がしてもよかつた筈なのに、頭に浮かんだのは呉の旅館の朝、飲んでゐるのだといふことだつた。それから起きて飲んだのが千福で、千福の味はここで改めて説明する までもない。おこぜの味噌汁が素敵だつた。ガラス戸越しに、呉を取り巻いてゐる丘が家で埋まつてゐるのが見えて、その時、やはり呉にゐるのだと思はなかつたのは、それは目を覺してゐた時から承知してゐたからである。例へばロンドンで朝起きると、自分がロンドンにゐるのを感じる。さういふものがない町は、本當を言へば、町といふものではない。呉の賑やかな通りには、何か寂しいものがある。これも一つの町が町である爲には大事なことで、昔は東京にもそれがあり、それで例へば、山手暮色といふやうな言ひ方にも意味があつた。今、新宿暮色だの、澁谷暮色だのと言つた所で、どれだけの實感があるだらうか。併し呉の大通りを夕方、歩いてゐれば寂しくなることが出来る。この寂しさがパリでパリの詩人達を育てたもの、又、パリ人にパリを愛させるものなので、ボードレールの「パリの憂鬱」といふ詩集の題は、詩人の氣紛れで付けたものではないのである。呉の人と特に聞いてゐる詩人はゐないが、それよりも大事なことに、呉では人間竝に、といふのは、二十世紀の文明人竝にその日その日を暮すことが出来るのを感じる。これは當り前なことだらうか。それでは、さういふ當り前な町が今日では餘りに少ないのである。」 [小澤書店刊、吉田健一著、『定本落日抄 (1976年)』p136-137]